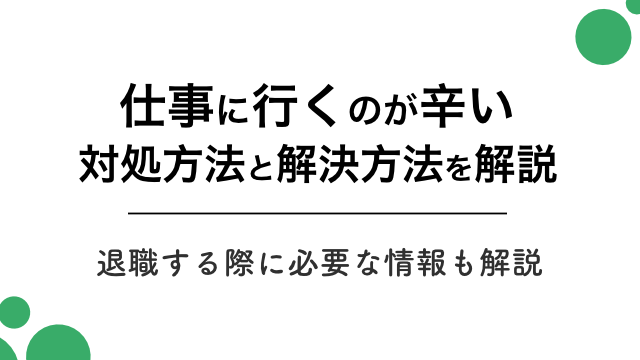仕事に行くのが辛いと感じている状態を放置すると、体調の悪化や仕事へ支障が出ます。
厚生労働省が公表した調査によれば、働く人の過半数が職場で強いストレスを感じており、とくに人間関係や業務量が主な要因とされています。
参照元:職場における心の健康づくり
無理に働き続けるのではなく、状況を正しく捉え、何を優先すべきかを冷静に判断することが必要です。
本記事では仕事を続けるべきか、休職や退職を考えるべきかを判断する方法や、退職を考えた時に必要な情報を紹介します。
- 出勤がつらいと感じたときに現れやすい体と心の変化
- 状態を記録する方法と、相談や受診につなげる考え方
- 年代や立場ごとに異なる悩みの傾向と体に出やすい症状
- 退職を検討するときの判断材料と制度の内容
- 自分で退職を伝えられない場合に利用できる支援の内容
仕事に行くのが辛いと感じたら今の状態を冷静に見直すことが重要
仕事に行くのが辛いと感じるときは、今の状態を整理することが重要です。
- 起床時に胃の不快感や吐き気を感じる
- 出勤の準備を始めると頭痛や腹痛が起きる
- 通勤中に動悸や手足のふるえが生じる
精神面では、以下のような症状が表れやすくなります。
- 職場を思い浮かべると涙が出る
- 不安が止まらず夜間に眠れなくなる
- 集中できずミスが続き、さらに自己否定が強まる
上記のような症状が出ているのにもかかわらず、無理に仕事を続けてしまうと心と体が限界を超え、取り返しがつかなくなります。
不調を自覚している時はもちろん、周りから心配されている場合は、仕事を続けるよりも医療機関に相談しましょう。
仕事が辛いと感じたときに確認する心や体の変化
仕事が辛いと感じたときは、心や体に表れる変化に気づくことが重要です。
状態を見過ごして働き続けると、不調が深刻になるおそれがあるため、早めに自分の変化を確認しておく必要があります。
とくに以下のような反応が出ている場合は、精神的な負荷が身体にも影響している可能性があります。
- 朝起きたときに吐き気や動悸がある
- 出勤前に涙が出たり、意欲が湧かなくなる
- 睡眠の質が下がり、休日でも疲れが取れない
- 通勤中に胸が苦しくなったり、不安になる
- 感情の波が大きく、怒りっぽくなったり落ち込んだりする
上記の反応はがある場合は気のせいと思わず、医療機関に相談するようにしましょう。
出勤前に心と体に異常が出たら無理をせず医療機関に相談する
出勤前に心身の異常が表れているときは、無理に職場へ向かわず、医療機関に相談することが重要です。
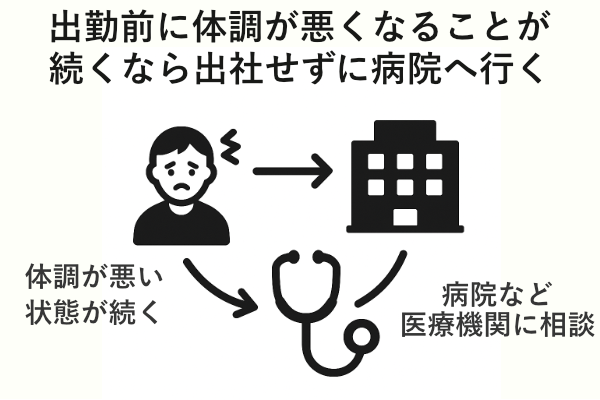
次のような兆候が見られる場合は、仕事を続けるよりも体調を優先する必要があります。
- 通勤途中に手足が震える
- 職場の最寄り駅が近づくと息が苦しくなる
- 出勤直前に涙が出る
- 起床後から頭痛や腹痛が継続する
上記の症状がある場合、体ではなく精神面の不調である可能性が高く、業務にあたれなくなる可能性があるからです。
医療機関を受診すると、以下のような支援が得られます。
| 支援内容 | 説明 |
|---|---|
| 心身状態の評価 | 医師の診察により、現在の状況を第三者の視点で整理できる |
| 診断書の発行 | 職場との交渉や休職手続きが進めやすくなる |
| 制度活用の準備 | 傷病手当金や就労制限申請の前提条件を整えられる |
| 行動判断の補強 | 医師の助言により、今後の選択肢が明確になり、家族にも共有しやすくなる |
診断を受けることで、回復の道筋を具体的に検討できるようになります。
正確な診断を受けるためにも、日頃の症状を記録しておくことも大切です。
症状が出た時間やきっかけを記録しておくと医師や会社へ説明しやすくなる
体調不良を言葉だけで伝えるのが難しいと感じたときは、症状の出た時間や直前の出来事を記録しておくことが重要です。
以下の項目を継続して記録しておくと、症状の整理がしやすくなり、医師の診察や職場へ説明がしやすくなります。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生した時刻 | 午前7時に腹痛が10分間などの具体的な時間表記 |
| 発生時の行動 | 通話中や会議中、通勤中など、症状の引き金となる行動 |
| 生活習慣の変化 | 睡眠不足や食事の乱れ、飲酒などの影響も記録する |
| 身体と感情の反応 | 動悸や倦怠感、不安や吐き気など、自覚した症状を記録する |
記録された内容は、HPS(ハミルトン身体症状尺度)など診断指標にも活用できます。
参照元:ハミルトンうつ病評価尺度の各項目による慢性痛患者のうつ症状と痛みの強さの程度の関係
HPSとは、以下の指標を身体症状から点数化し、精神的ストレスやうつ傾向を評価する心理尺度のことです。
- 身体症状を点数化して評価する
- 精神的ストレスや抑うつの傾向を測定する
- 医療機関での診断補助として使用されている
医師もHPSを利用することで、問診では判断しにくい症状も把握できるため、正しい診断や治療方針を立てられるようになります。
つらさの原因をセルフチェックで整理する方法
仕事がつらいと感じているのに、理由がはっきりしないままでは対処の方向が見えません。
以下のような観点から記録しておくと、原因の把握や相談時の説明がしやすくなります。
セルフチェック表
| 確認項目 | 記入例 |
|---|---|
| つらく感じ始めた時期 | 3週間前から毎朝動悸が出るようになった |
| 仕事がつらくなった直接的な出来事 | 上司に怒鳴られて以降、緊張が取れない |
| 身体に現れている反応 | 不眠、吐き気、食欲低下 |
| 心理的な負担を感じている職場の要素 | 業務量の多さ、人間関係、評価制度への不満 |
| 今までに試した対応策 | 上司に相談、人事へ異動希望、休暇申請 |
記録が整っていれば、医療機関や職場と相談する時、詳細に状況を伝えられるようになります。
他にも厚生労働省が提供している、5分でできる職場のストレスセルフチェックも有効です。
セルフチェックの結果がどうであれ、仕事の行くのが辛い状態は誰にもでも起こることだと知りましょう。
仕事に行くのが辛いと感じる状態は特別なことではない
仕事に行くのが辛いと感じることは特別なことではなく、誰でも経験があることです。
厚生労働省の調査では、現在の仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスがあると回答した人の割合は全体の53.3%にのぼります。
背景には、業務量や人間関係による負担が関係しており、継続すれば心身に影響が出るおそれがあります。
調査では、主なストレスの要因として次の項目が挙げられています。
| ストレスの要因 | 該当者の割合 |
|---|---|
| 業務の量が多い | 39.4% |
| 職場内の人間関係の問題 | 29.6% |
ストレスの要因はどの職種にも共通しており、働き方や職場環境によってストレスの現れ方が変わることがわかります。
心身への影響としては、次のような症状が出ることがあります。
- 集中力の低下
- 作業ミスの増加
- 不眠や睡眠の質の低下
- 食欲の変化や消失
上記のような症状が続いているときは、現在の仕事と体調の関係を冷静に見直すことが求められます。
属性別に見ても、ストレスの受け止め方や影響には違いがあり、年代や性別による傾向を把握することも重要です。
若年層や女性は仕事への悩みを抱えやすく不調に陥りやすい
20〜30代と女性は、身体的疲労や睡眠の質の低下といったストレス反応が生じやすく、早期対応が重要になります。
女性労働者の間で心身の疲労や不眠の訴え、症状の割合は次のとおりです。
| 症状 | 該当者の割合 |
|---|---|
| 疲労感 | 70.6% |
| 筋骨格系症状や頭痛 | 68.1% |
| 不眠症状 | 33.0% |
参照元:日本人女性労働者の就労上課題となる生物心理社会的な要因
上記のような症状が重なりやすい背景には、業務量に対する裁量の少なさや、私生活との両立による慢性的な疲労があります。
例えば女性の場合、家庭や育児の責任と仕事の両立に悩みを抱えています。
体調や感情の変化が続く場合は、不調の兆候を見逃さずに行動することが大切であり、次のような取り組みが効果的です。
- 業務量や勤務時間の見直しを上司と相談する
- 心身の症状について産業医に報告する
- 職場外の支援窓口を利用し、状況を共有する
負担を軽減するためにも、自分の状況や状態を把握し、健全な働き方につなげましょう。
職場環境や働き方の違いによって心身に与える負担は個々で異なる
職場での働き方の違いによって、身体や精神に感じる負担は個々に異なります。
厚生労働省が公表した過重労働とメンタルヘルスに関する調査では、長時間労働や交代勤務を続けることで、睡眠の質の低下やストレスが増幅しやすくなるとされています。
参照元:過重労働とメンタルヘルス
働き方の違いが与える、主な影響は以下のとおりです。
| 働き方の違い | 心身に現れやすい影響 |
|---|---|
| 交代勤務 | 睡眠リズムの乱れと慢性的な疲労 |
| 長時間労働 | 判断力の低下や継続的な集中困難 |
| 人間関係が乏しい職場 | 相談機会の減少と精神的な孤立感の強まり |
勤務条件と体調の関係に気づかず過ごしていると、生活全体に支障をきたすことがあります。
職場のルールや勤務体系に身体が合っていないと感じるときは、制度の変更や配置の調整を視野に入れる必要があります。
自分に合う働き方へと進むために、社内外で活用できる具体的な支援制度や相談先を利用しましょう。
自分に合った働き方を選ぶには社内外の支援制度を活用する
働き方が自分に合っていないと感じたときは、環境そのものを見直すことが必要です。
不調の原因が業務量や勤務時間、人間関係にある場合には、制度や仕組みを活用することで負担を軽減できる可能性があります。
厚生労働省が公表している支援制度には、事業所内で利用できる仕組みに加えて、外部機関に相談できる体制も整えられています。
| 支援の種類 | 主な内容・利用場面 |
|---|---|
| 産業医・保健師との面談 | 心身の不調を早期に相談し、職場調整につなげる |
| 職場復帰支援プログラム | 休職中の社員が無理なく復職できるよう支援 |
| 地域の相談支援窓口 | 勤務条件や健康問題に関する相談全般 |
参照元:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(厚生労働省)
支援制度は自ら申し出が必要ですが、疲労やストレスを感じているのであれば、早めに活用することで悪化を防ぐことが可能です。
制度の存在を知っておくだけでも、働き方を変えるきっかけとなるでしょう。
状況が変わらないときは退職や転職も検討の対象にできる
現在の職場で不調やストレスが改善しない場合には、退職や転職を選択肢に入れることが重要です。
厚生労働省が公表している調査によると、長期間の職場ストレスが続いた際に離職や転職により健康状態が回復した事例が報告されています。
退職や転職を判断する際には、次のような状態や期間を目安にすることで判断が可能です。
| 判断の目安 | 対応の方向性 |
|---|---|
| 原因の改善を試みても効果が出ない | 部署異動や職場内の相談窓口利用を検討する |
| 不調が数週間以上継続している | 一時的な休職や退職も選択肢に加える |
| 出勤が難しいレベルで業務に支障が出ている | 転職による職場環境の変更を本格的に検討する |
まずは身体の反応や日常生活への影響に目を向けることで、現実的な対応が見えてきます。
無理に続けることを前提にせず、健康を守る視点で環境の見直し、行動することが大切です。
退職を検討するときは法律と制度を理解したうえで準備を進める
退職を選択肢に入れるときは、感情だけで判断せず、法律や制度を理解したうえで計画的に進めることが大切です。
手続きに不備があると、必要な権利が受けられなかったり、会社との間で問題になるおそれがあります。
労働契約の終了については、民法第六百二十七条において、労働者が退職の意思を伝えた日から2週間を経過すれば契約を終了できるとされています。
会社ごとに就業規則などだけでなく、以下の整理しておく項目と対応を準備しておくことが必要です。
退職に向けて整理しておく項目
| 整理しておく項目 | 対応 |
|---|---|
| 退職日をいつにするか決める | 退職届の提出日から逆算して準備期間を確保する |
| 会社の就業規則を確認する | 引き継ぎや書類提出に関するルールを把握しておく |
| 有給休暇の残日数を確認する | 退職前に消化可能かを確認し、損失を避ける |
上記をおさえた上で退職を進めれば、自分にとって不利のない形で退職できます。
ただし、傷病手当や失業給付を受ける場合は上記の項目以外にも、利用条件の事前確認が必要です。
退職後に傷病手当や失業給付を受けるには制度の条件を確認が重要
退職後に申請できる代表的な制度には、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業給付があります。
退職後に経済的な支援を受けるには、制度ごとの条件と手続きを正しく把握しておくことが必要です。
| 制度名 | 主な対象者 | 支給条件の概要 | 必要書類と準備期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険に加入していた人 | 退職前から受給中であり、資格喪失日後も継続条件を満たす場合に支給可 | 医師の意見書・健康保険資格喪失証明書など(取得に約1週間〜10日) |
| 失業給付 | 雇用保険に1年以上加入していた人 | 退職後に求職の申し込みを行い、失業状態であることが条件 | 離職票・本人確認書類など(離職票の到着に1〜2週間かかることがある) |
上記の制度は、退職日や受診開始日、保険の加入状況などによって受給の可否が変わります。
退職前に申請条件や必要な書類を確認しておけば、申請の遅れや支給の中断を防ぐことができます。
不測の事態に備える意味でも、制度の内容と自分の状況を照らし合わせて準備を進めることが重要です。
退職後は生活習慣を整えながら次の働き方を見直すことも重要
退職後に心身を整えるには、生活習慣を安定させながら次の働き方を見直すことが重要です。
退職後の生活を安定させるには、以下のような取り組みが必要となります。
- 毎朝同じ時間に起床し、朝日を浴びて体内時計を整える
- 寝る前は明るい画面を避けて、一定の時間に就寝する
- 食事は朝昼晩に分けてとり、主食や主菜、副菜をそろえる
- 日中に散歩や体操など、軽い運動を取り入れて活動量を保つ
上記の習慣を続けると、体調が安定し、次の職場を選ぶ判断も冷静におこなえるようになります。
退職まで円滑に進めばよいのですが、会社に退職の意思を伝えにくいのであれば、退職代行を利用するのも一つの方法です。
自分で退職を伝えるのが難しい場合は退職代行を利用する
退職の意思を伝えることに抵抗があるときは、退職代行を利用することで会社とのやりとりを避けて手続きを進められます。
出社や電話対応を省けるため、精神的な負担を減らしたい場合にも有効な手段です。
業者によっては、有給休暇の取得や未払い金の交渉にも対応しています。
退職代行サービスは、以下表のように費用や対応範囲が異なります。
| 業者名 | 費用(税込) | 交渉対応 | 即日対応 | 運営主体 |
|---|---|---|---|---|
| EXIT | 20,000円 | 不可 | 可 | 民間企業型 |
| 退職代行SARABA | 24,000円 | 可 | 可 | 労働組合型 |
| 弁護士法人みやび | 27,500円〜+実費 | 可 | 可 | 弁護士法人型 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 不可 | 可 | 民間企業型 |
| わたしNEXT | 26,800円 | 可 | 可 | 労働組合型 |
| 男の退職代行 | 26,800円 | 可 | 可 | 労働組合型 |
| 即ヤメ | 19,800円 | 不可 | 可 | 民間企業型 |
退職代行を選ぶときは費用だけでなく、交渉対応の有無や対応時間も含め、総合的に判断することが大切です。
EXITの料金は、正社員とアルバイトで同額となっており、立場を問わず一律の金額で利用できます。
EXITは利用者数が多く20,000円から依頼できる退職代行

EXITは、利用者の多い退職代行であり、20,000円から依頼できます。
退職を伝えることができず悩んでいる人でも、会社とのやりとりをすべて任せられる仕組みになっています。
業界で最初に退職代行を専門に始めた業者であり、累計の利用件数は3万件を超えています。
正社員でもアルバイトでも、料金は税込20,000円で統一されており、申し込み後に追加費用は発生しません。
会社への連絡はすべてEXITが行うため、本人が電話やメールを使う必要はありません。
申し込みから手続き完了まで、LINEやメールのやりとりだけで対応できます。
EXITは24時間いつでも申し込みが可能であるため、前日の深夜や当日の早朝に手続きしても、即日に対応してもらえる退職代行です。
EXIT 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 20,000円(正社員・アルバイト共通) |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 非対応 |
| 受付方法 | LINE・メール |
| 受付時間 | 24時間 |
退職代行SARABAは労働組合の交渉権限によって有給取得の交渉にも対応できる
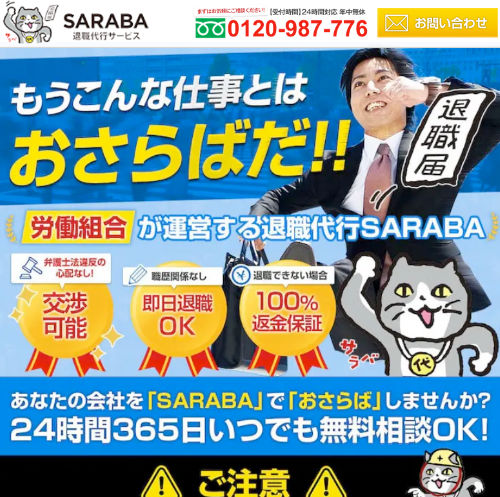
退職代行SARABAは、交渉権限を持つ労働組合が運営しており、有給取得の交渉にも対応できる退職代行です。
費用は税込24,000円で、正社員でもアルバイトでも同じ金額で利用できます。
労働組合法にもとづいて会社との交渉を行えるため、依頼者の代わりに有給の消化や未払い賃金に関する主張を正式に伝えられます。
本人が会社とやりとりをしなくても、手続き全体を代行してもらえる点が特徴です。
申し込みはLINEやメールで完結でき、電話のやりとりも必要ありません。
24時間いつでも申し込みが可能であり、即日の対応にも柔軟に応じています。
退職代行SARABA 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 24,000円(正社員・アルバイト共通) |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 対応可能(労働組合による運営) |
| 受付方法 | LINE・メール |
| 受付時間 | 24時間 |
弁護士法人みやびは損害請求など法律に基づいて手続きできる

弁護士法人みやびは、未払い金や損害請求など法律に基づいて交渉を任せられる退職代行です。
対応はすべて弁護士がおこなうため、請求書や内容証明の送付も正式な手続きとして進められます。
一般の退職代行では扱えない損害賠償や慰謝料の問題にも対応でき、法的な支援を必要とする人に最適です。
会社との連絡はすべて弁護士が担当し、本人はLINEやメールだけで退職手続きを開始できます。
料金は会社員やアルバイトで会社と交渉がなければ、27,500円で利用できます。
交渉の結果、未払金などを回収できた場合、成功報酬として回収費の20%が実費として支払いが必要です。
弁護士法人みやび 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | ・会社員、アルバイト、契約社員など 27,500円/交渉なし 55,000円/交渉あり ・自衛隊、業務委託、会社役員など 77,000円/交渉あり 上記に成功報酬として、回収費用の20%を請求。 |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 対応可能(弁護士による法的対応) |
| 受付方法 | LINE・メール |
| 受付時間 | 24時間 |
退職代行モームリは12,000円から利用でき転職支援も受けられる

退職代行モームリは、アルバイトなら12,000円から利用でき、退職後には転職支援も受けられる退職代行です。
正社員や契約社員、派遣社員の場合は22,000円で依頼できます。
いずれのプランも追加費用は一切発生せず、利用後に請求が増えることもありません。
転職を希望する人には、提携エージェントによる求人紹介や応募書類の添削支援が用意されています。
申し込みはLINEやメールで完結し、24時間受け付けているため、夜間や休日でも即日に対応してもらえます。
退職代行モームリ 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 12,000円/パート、アルバイトの場合 22,000円/正社員、契約社員、派遣社員の場合 |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 非対応 |
| 受付方法 | LINE・メール |
| 受付時間 | 24時間 |
| 付帯支援 | 転職支援あり/退職できなければ全額返金保証付き |
わたしNEXTは女性スタッフが対応するから悩みを相談しやすく退職後も支援が受けられる

わたしNEXTは、すべての対応を女性スタッフが行っている女性専用の退職代行です。
職場での人間関係やストレスによる負担が重なり、自分で退職を伝えるのが難しいと感じた女性が安心して相談できる体制が整っています。
退職手続きはLINEか専用フォームから申し込み、やり取りはすべて代行されます。
希望すれば即日対応も可能で、深夜や休日にも申し込みができます。
正社員や派遣社員などは25,800円、アルバイトやパートで社会保険に未加入の人は18,800円で利用できます。
別途1,000円の組合費が必要ですが、万一退職できなかった場合には全額返金制度も適用されます。
退職後の転職活動を支援する無料サポートも用意されており、次の働き方へ進みたい人にとって心強い退職代行です。
わたしNEXT 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 正社員や契約社員:25,800円+組合費1,000円 アルバイトやパート(社会保険未加入):18,800円+組合費1,000円 |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 労働組合による対応が可能 |
| 受付方法 | LINEや専用フォーム |
| 受付時間 | 24時間対応 |
男の退職代行は男性の悩みに特化しており即日で退職の負担を軽減できる
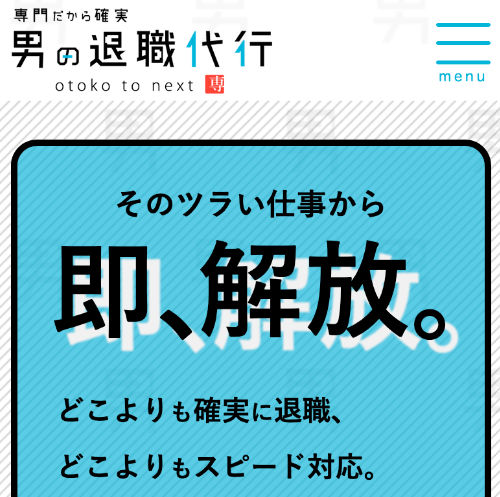
男の退職代行は、男性の退職理由に多い上司との関係や長時間労働などに対応するために設立された業者です。
労働組合が運営し、弁護士の指導を受けているため、会社との交渉が必要な場合でも適切に対応してもらえます。
料金は、正社員や派遣社員など社会保険加入者が25,800円、アルバイトやパートで未加入の場合は18,800円となっており、別途1,000円の組合費がかかります。
即日対応にも対応しているため、翌日から出勤せずに退職手続きを進めたい場合にも利用しやすい業者です。
退職成功率は100%と公表されており、万が一退職ができなかった場合には全額が返金される制度も用意されています。
男性の悩みに寄り添いながら、円滑に退職を支援してくれる退職代行です。
男の退職代行 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 正社員や契約社員:25,800円+組合費1,000円 アルバイトやパート(社会保険未加入):18,800円+組合費1,000円 |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 労働組合による対応が可能 |
| 受付方法 | LINEや専用フォーム |
| 受付時間 | 24時間対応 |
即ヤメは退職後の支払いができる後払い制で早朝や深夜でも即日対応してもらえる

即ヤメは、今すぐ会社を辞めたい人に向いている退職代行です。
料金は後払いで、退職手続きが完了してからの支払いになるため、金銭的な余裕がなくても依頼しやすい特徴があります。
料金は一律20,000円でLINE相談ややり取りはすべて任せられだけでなく、退職できなかった場合は料金が返金されます。
受付は24時間対応で、早朝や深夜でも即日に退職を進められる退職代行です。
即ヤメ 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(税込) | 20,000円(後払い) |
| 会社との連絡 | すべて任せられる |
| 即日対応 | 対応可能 |
| 交渉対応 | 非対応(連絡代行のみ) |
| 受付方法 | LINE |
| 受付時間 | 24時間対応 |
仕事に行くのが辛いと感じたときによくある質問
仕事に行くのが辛いと感じているときは、考えがまとまらず判断に迷うことが多くなります。
以下の質問を整理しておくと、自分にとって何を優先すべきかが見えてきます。
出勤前に動悸や吐き気が続く状態でも仕事を続けるべきですか?
身体が強い負荷に反応しているときは、無理に出社を続けることで症状が悪化するおそれがあります。
まずは数日でも休養を取り、状況が変わるかどうかを観察することが必要です。
朝に体調が崩れる傾向が続いているなら、勤務時間の変更や医療機関の受診を検討する段階に入っています。
自律神経の乱れや抑うつ状態が背景にある場合もあるため、自分の変化を正しく受け止めることが大切です。
精神的に限界を感じていても、すぐに辞めるのは早い判断になりますか?
いきなり退職を決断する前に、まずは数週間の休職や業務の調整など、選択肢を並べて比較することが望ましいです。
休職制度を利用することで、働きながら考える時間を確保できるうえ、収入面での不安も軽減できます。
判断を急ぎすぎると、後悔や経済的な問題が大きくなる可能性があります。
状況に余裕が残されているなら、継続・休職・退職の選択肢を一度に排除せず、時間をかけて比較する姿勢が必要です。
症状の内容をうまく説明できないため、病院や相談窓口に行く自信がありません
症状を言葉にするのが難しいと感じているときは、日時と状況を記録しておく方法が効果的です。
たとえば、出勤前の吐き気が3日続いた、会議後に強い疲労感があったなど簡潔なメモでも十分に伝わります。
医師や相談員も記録があることで状況を把握しやすく、より的確なアドバイスが受けられるようになります。
言葉が出てこない状態に悩む必要はなく、記録が代わりになる手段として活用しましょう。
職場の人間関係が原因で出社が困難になってきました
人間関係の負担は精神面だけでなく、身体的な反応にもつながります。
退職を選ぶ前に、配置転換やチーム変更などの選択肢を上司に相談できるかを検討してみてください。
問題の相手と距離を取れるだけでも、症状が軽減されることがあります。
相談が難しいと感じる場合は、社内の人事窓口や社外の労働相談機関を活用する方法も有効です。
辞めたい気持ちはあるのに、生活や将来の不安で動けずにいます
精神的な負荷が限界に近づいているときは、まず自分の健康を守る行動を最優先に考える必要があります。
退職後に使える制度としては、傷病手当や失業給付が代表的です。
それぞれ条件や期間が異なるため、事前に制度の内容を調べておくと、収入の見通しを立てやすくなります。
以下では、年代や職種の異なる4人がどのように状況を乗り越えたのかを紹介します。
仕事に行くのが辛かったときに退職を選んだ人の体験談
仕事に行くのが辛いとき、退職という選択を取った人の体験談を紹介します。
以下では、年代や職種の異なる4人の体験談を紹介、参考にしてみてください。
30代女性 事務職/退職後に心身の負担が減り生活に落ち着きが戻った
朝になると涙が出る日が続き、出勤前に気力が湧かなくなったことが退職のきっかけでした。
仕事の内容よりも、人間関係や雑務の多さによって気持ちに余裕がなくなっていました。
当時は退職すれば生活が崩れると感じていましたが、体調の悪化を放置するほうが危険だと気づきました。
退職後はまず睡眠や食事の時間を整え、ゆっくりと生活のリズムを取り戻しました。
休む期間を通じて体調が改善し、自分に合った働き方を探そうという意欲も戻ってきました。
現在は短時間の勤務で働いており、無理のない生活を続けられています。
20代男性 営業職/勇気を出して退職し自分に合う働き方を見つけた
上司との関係や長時間労働が続き、出勤中に電車を降りて動けなくなったことが転機になりました。
体調も不安定になり、会社に連絡することさえ怖くなっていました。
最初は退職への不安が強く、行動に移せませんでしたが、家族や外部の相談窓口に話を聞いてもらううちに冷静になれました。
数週間かけて退職を決断し、自分の生活や気持ちに合う働き方を考え直しました。
現在は在宅勤務の仕事に就いており、通勤の負担もありません。
無理をせず働ける環境に変えたことで、心身の不調が徐々に回復しています。
40代男性 技術職/突然の不調で休職し職場との関係を見直した
勤続20年を超えても仕事を続けるのが当たり前だと考えてきましたが、ある日突然、身体が動かなくなりました。
医療機関での診断結果は過労による抑うつ状態で、休職を強く勧められました。
復帰後も不安が消えず、勤務時間や業務内容を上司と相談し、配置転換によって負担を軽減することができました。
長く勤めていたとしても無理をすれば崩れるという現実に向き合い、自分の体調と働き方を調整する視点を持てるようになりました。
20代女性 接客業/アルバイトを辞めて生活の軸を立て直した
もともとは就職活動の準備期間中に始めたアルバイトでしたが、次第に勤務日数が増えて心身が追いつかなくなりました。
忙しさに耐えて働き続けていましたが、体調を崩して初めて限界に気づきました。
継続することが自分にとって本当に必要かを疑問に感じ、契約を終了することにしました。
辞めてからは生活のリズムを整え、資格の勉強をしながら次の目標を定めています。
あのとき辞めなかったら今の自分はなかったと実感しています。
仕事に行くのが辛いときは自分を守る行動を最優先に考えることが重要
仕事に行くのが辛いと感じたときは、体や心に出ている変化を受け止めることが大切です。
疲れや不眠などの症状を放置すると、働き続けるのが難しくなる場合があります。
負担の原因を見直し、今の働き方を冷静に考え直すことで、行動の選択肢が見えてきます。
休養を確保する、上司に相談する、制度を調べて利用するなど、自分にできることから試すことが必要です。
状況が変わらないときは、退職や転職も含めて将来を立て直す選択を検討しましょう。
ひとりで抱え込まず、周囲の支援や外部のサービスも使いながら、自分の負担を減らすことを優先する姿勢が大切です。